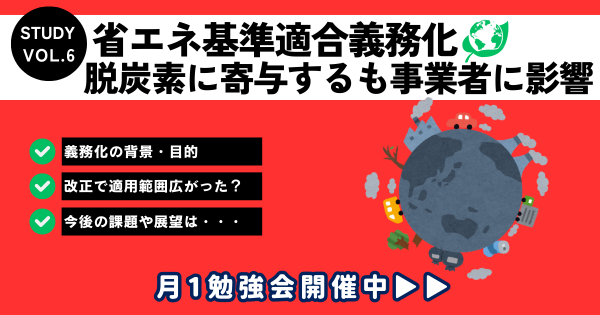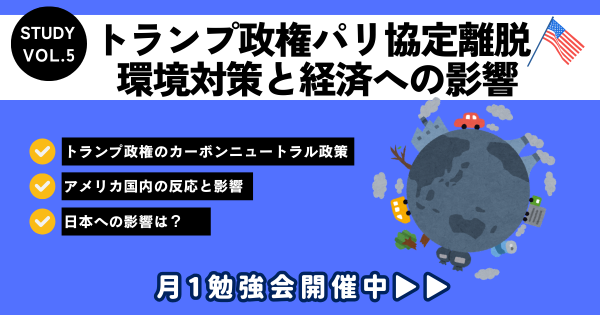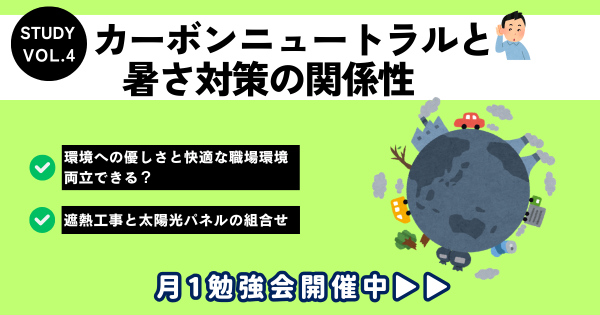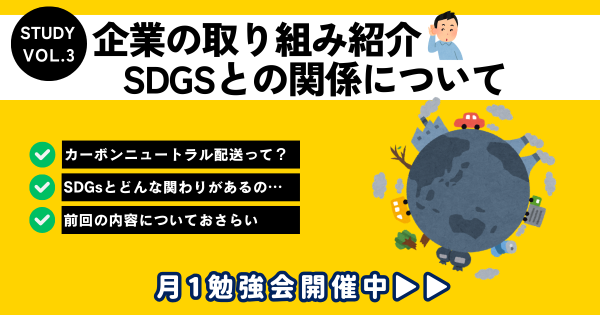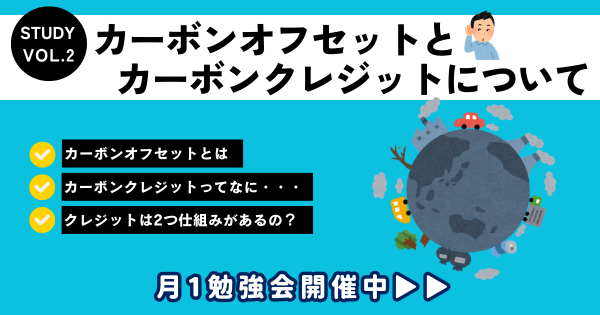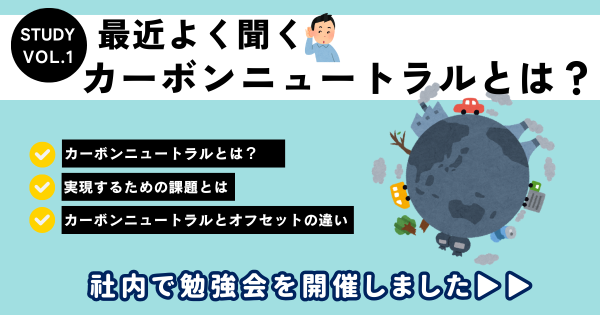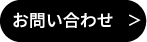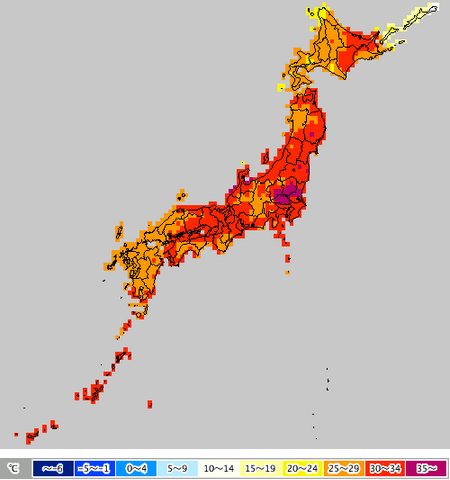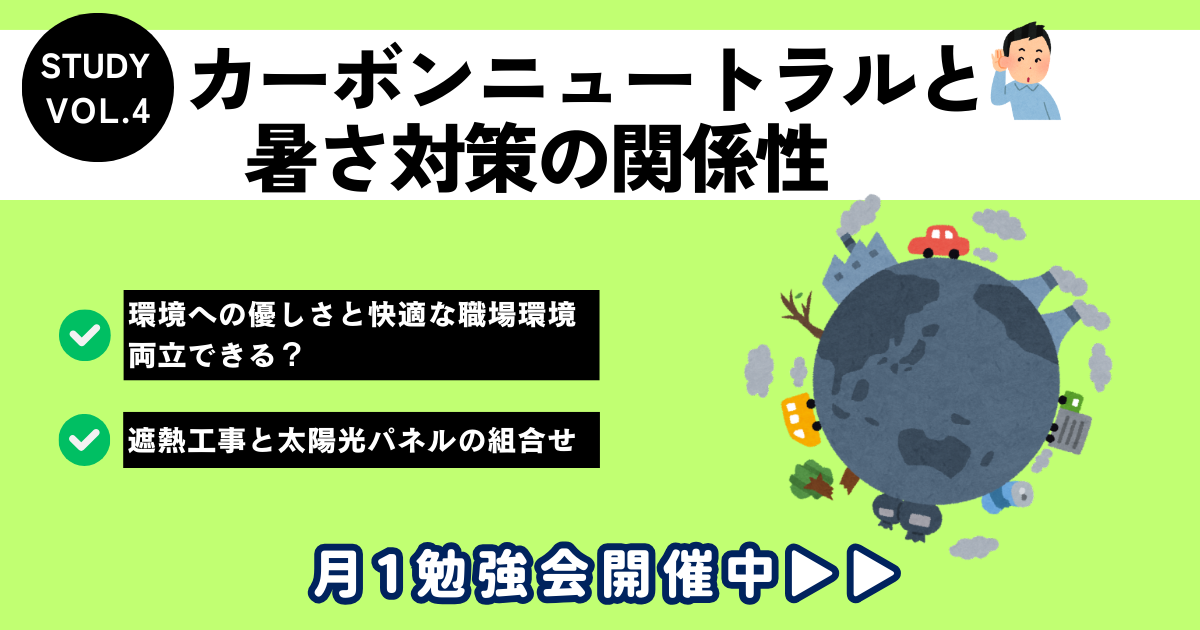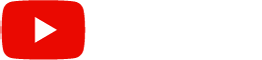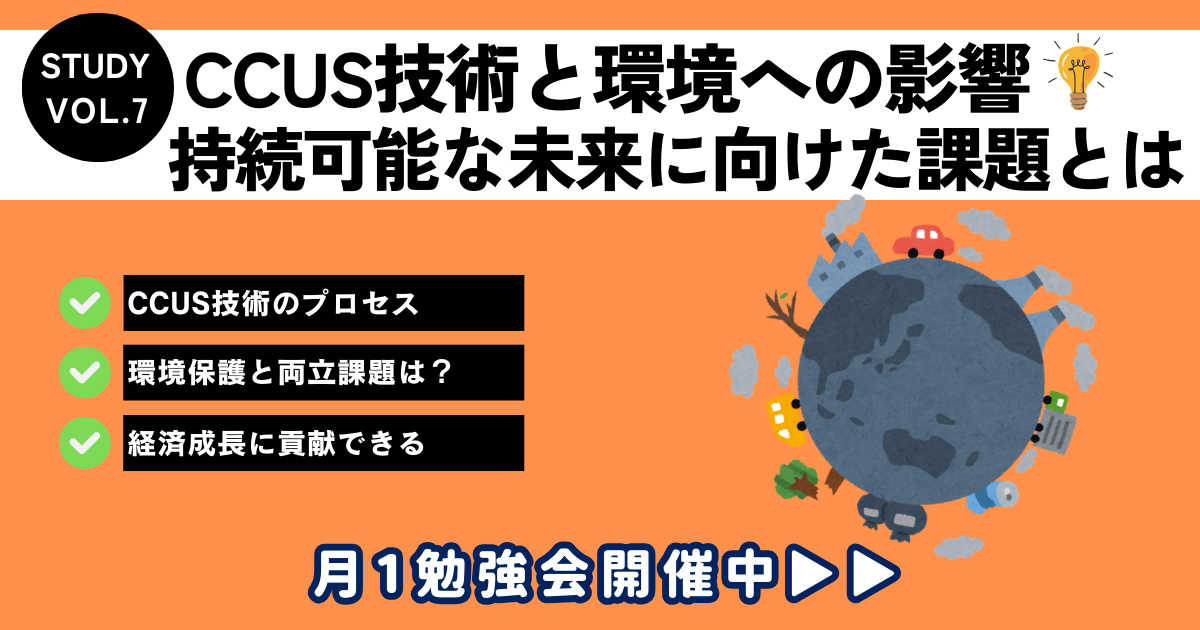
開催日:2025年4月11日(金)
参加者:4名
今回の勉強会では、CCUS技術とは何か、またその技術が経済成長や環境保護にどのような影響を与えるのかをテーマに勉強しました。
CO₂削減の有力な技術なのですが、環境との両立にはたくさんの課題も…

CCUS(Carbon Capture, Utilization, and Storage)とは
二酸化炭素(CO₂)を回収し、利用するか安全に貯留する技術の総称です。カーボンニュートラルの実現に向けた重要な手段の一つとして注目されている。
CCUSの主なプロセス
回収(Capture)
- 工場や発電所などの排ガスからCO₂を分離・回収
- 直接空気中から回収
利用(Utilization)
- CO₂を合成燃料、化学製品、建材に再利用
- バイオ燃料生産や藻類培養への活用も研究されている
貯留(Storage)
- 地下深部の地層(枯渇油田・ガス田、塩水層など)にCO₂を圧入して長期貯蔵
- 海底貯留の技術開発も進行中
CCUS技術 経済成長への貢献
(1) 産業利用と新市場の創出 (CCUS技術はCO₂削減だけでなく新たなビジネス機会を生む)
合成燃料→CO₂を利用して合成燃料(合成ガソリン、ディーゼル、航空燃料など)を製造する技術は、化石燃料の使用を減らしながら、既存のインフラを維持することができる
化学製品→CO₂を化学的に転換して化学製品の原料や、炭酸飲料・冷却剤などの製品に利用する技術が進んでおり、CO₂は石油や天然ガスの代替として活用可能(プラスチックは開発段階)
建築材料→CO₂を利用してコンクリートやセメントの強度を向上させ、建設業のカーボンフットプリントを削減し、CO₂を製品に組み込んで永久に封じ込める技術が進んでいる
※建設業のカーボンフットプリント(CFP)とは、建設工事のライフサイクル全体で排出される温室効果ガス(CO2)の量を定量的に算定したもの
(2)雇用と経済波及効果
・CCUS関連の技術開発・インフラ整備に伴う新たな雇用創出
・CCUSを活用することで、排出量取引市場での収益化が可能
環境保護との両立課題
(1) CO₂回収プロセスのエネルギー消費
・CO₂の分離・回収には大量のエネルギーが必要
・CCUSの導入はエネルギーコストの上昇を招く
・火力発電所や工場では追加の燃料消費によるCO₂排出増加の可能性
(2)CO₂の輸送・貯留の環境リスク
・CO₂を輸送・貯留するためのインフラ整備(パイプライン・貯留施設)が必要
・地下貯留時の地震や漏洩リスク(地圧変化による影響)
・海底貯留の影響が海洋生態系に与える影響は不明確
(3) CO₂の利用による新たな環境負荷
・CO₂を利用して合成燃料を作る場合、燃焼時に再びCO₂を排出する
・CO₂を化学品やプラスチックに利用すると、廃棄時の環境負荷が増える可能性
・CO₂利用が短期的な炭素循環に留まり、長期的なCO₂削減に繋がらない可能性
(4) 経済性と環境負荷のバランス
・CCUSの導入コストが高く、企業の負担になる
・↳ 排出削減よりも排出権購入を選択する企業が増える可能性
・CCUSの投資回収が長期化すると、開発が進まないリスク
まとめ
CCUSは、CO2削減や環境保護に有効な技術であり、カーボンニュートラル実現に貢献する。しかし、高コストや貯留リスクの克服が必要。持続可能な未来を目指すためには、技術革新と政府等の支援が成功の鍵となる。
感想
CCUSという取り組みは一般的に活用されていくには、まだまだ多くの課題があると感じましたが、これからの研究や技術革新によってこの取り組みが広がりを見せ地球温暖化へと繋がっていけばいいなと感じました。
二酸化炭素を地中に埋めてしまうという視点には驚きました。現状、雀の涙のような成果だと感じ、この研究が今後本当に役立つのか正直わからないですが、より効率的な回収方法も研究されていくでしょうからカーボンニュートラルの取り組みが一層前進することを信じたいと思います。
CCUSは、今はまだ課題も多くメリットよりデメリットが目立っているような気がしますが、カーボンニュートラルを実現するには必要な技術だと思いますし、そのために技術開発が進められていると思います。これから課題が少しずつ解決されて、もっと使いやすく、広く活用されるようになればいいなと思います。
このような取り組みがされていることを初めて知りました。総額300億円という壮大なプロジェクトが実証実験としてされているとのこと。今は、効率的とは言えない段階でありながらも、このような挑戦的な取り組みを継続し、改善していくことが重要なんだと思えました。未来の地球環境のために、いろんな企業がいろんな取り組みをしている事例を学ぶことは、とても勉強になります。
参考にしたサイト
経済産業省 資源エネルギー庁
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ccus.html
産総研マガジン
https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20220907.html
これまでの勉強会一覧🔻画像クリックで記事を読む